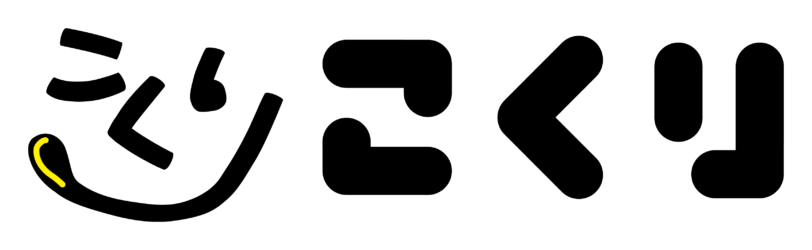キキにとって友達とは何でしょうか?
考えてみました。すきな物が似ている人、同じ趣味がある人、
苦手なことが似ている人、最近ハマったと?、金銭感覚が合う人?、つきあいが長い人?
いろいろ思い浮かびます。
でもそう考えた時にウマが合わない人でも「友達」と呼べる人もいるなぁとも思いました。
じゃあ友達ってなんなんや…また最初の考えに戻ってきました。
えぇ…改めて考えたことなかったので相当難しいですね。
ちょっとじっくり時間をかけて、休日に散歩したり、ぼーっと景色を眺めたり、本をよんだりなんかして考えてみました。
たぶん、今の私のなかでの「友達」は「私とあなたが対等に話せる間柄」なんじゃないかなというふんわりした考えがうまれました。でも「対等」って私が一方的に思うだけ、一方通行のときもあって、それって結局対等なんかなぁとも思います。いやー難しい。
答えらしいものはできなかったですが、今のキキの考えはこんな感じやと思いました。
暑さに勝てない。けど負けもしなさそう
どうも。「かんりしゃ」です。
暑すぎる。地球温暖化やばい!と言いつつクーラーで冷えた部屋にいる何とも言えなさ。
「かんりしゃ」の仕事に、在宅の部材運びと納品などがあります。
これがとにかく暑い!!汗だく!!汗くさくなる!!!Tシャツの着替えが必要です。
まぁ夏やな、しゃあないな、と思うと同時にやっぱり暑すぎな気もします。
人類、どこかの時点でやり方ミスってへんか、と思わされます。。。
地球は、そんな人類のやり方なんかへっちゃらなのか、やっぱり地球でもこたえるものなのか、別に人類主導の地球でなくてもよいのか。。。
こうも暑いと、思考の規模が広く広くなりますね。
「かんりしゃ」は、自分のもっとうとして、世界は一生かけてもみられないくらいとてつもなく広いし、目の前の世界にも無限の可能性が広がっていると思ってます。だからどちらも大切です。
だから何ってことはないのですが、とにかく暑い!ということを言いたいのです。
何かやばそうだぜ。けど日々を過ごすぜ。
友だちブログ 「3時のカフェイン」の場合
「友達」にもいくつかの種類があるのかな、と思いました。
気を許し合える親しい相手、会えば世間話するくらいの相手など、距離感は色々かもしれません。
そういった関係ぜんぶひっくるめて友達と言えてしまうというか。
自分の感覚になりますが、大人になるほど前者の「気を許し合える親しい」友達を作るのが難しくなっているような気がします。
気恥ずかしさとか、勇気が出ないとか、ちょっと面倒くさいとかそういうものに勝てなくなったのかな、と思ったりします。
大人になっても身軽に友達をつくったり、何ならその日たまたま出会った全くの他人と仲良くなったりする人もいるからすごいですね。
うらやましいような、そうでもないような。
こう考えてみると、人によって「友達」の範囲も基準も全然ちがうのかもしれません。
例えば、友達と顔見知りの境界もはっきりとは無いから、やっぱり人によって違うでしょうし。
ある意味ものすごく自由な概念なのかもしれません、友達。
友だちブログ 説明
どうもです、スタッフのちゅんです。
いきなりですが、”友だち”って何でしょう。当たり前の存在でありながら、改めて考えるとよく分からない存在だったりもして、なかなか難しいですよね。かく言う僕もそれについてよく悩んでおり、その旨をちょこちょこかんりしゃさんに相談していたところ、「では、ちゅんも含めた色んな人に”友だち観”について文章を書いてもらおう!」という本企画が生まれたのです。ということで今回は、立場や境遇の異なる全〇人の方に、”友だち観”について書いてもらいました。それぞれの個性が光り、多様な”友だち観”に触れることができると思いますよ。是非読んでみてください。
第4回 こくりの大発表会 ①
どうも。「かんりしゃ」です。
年に1度のこくりの一大イベント、大発表会が少しずつ近づいてきました。
今年のテーマは「うつ」です。
宣伝も兼ねて、いろいろと記事を書いていこうと思います。
なぜ「うつ」にしたのか。
それは、いろいろな意味で誤解をまねきやすいものだと思ったからです。
誤解①
「落ち込み」と「うつ症状」が似たようなものとみなされる
誤解②
「(内因性)うつ病」と「うつ症状」が同じものとみなされる
これらのことが、ある程度正確に伝わる会になればと思っています。
誤解①や②の詳しいことは、ぼちぼちブログに書いていきます。
また、他の大発表会のことについても書いていきます。
みなさま、ぜひお越しください。
よろしくお願いします。


みんなの「こくりらしさ」写真展
どうも。「かんりしゃ」です。
金曜日、みんなで「こくりらしさ」をテーマに写真撮影会をしました。
それぞれの見え方が出ておもしろい。

一番最初に目に入るところ

みんなでやるカレーと、個人プロジェクトのものがあるのがこくりらしい

カレー屋と当事者研究をしてるのが、こくりらしい

みんなの作品。エレベーターを降りて最初にめがいくところ

いつもはカレーでパンパン。今日はカレーが入ってない

こくりを始める時に一番最初に買ったものたち

2階からの景色。すごいところに物を置いていて雑多さがあらわれてる。

紙のペーパーのストックがたくさんあるのがこくりらしい
以上です。
それぞれで、おもしろいねー。
「ゼロカロリーのピーちゃん」のひまわり物語2024 ③
2024年7月1日
どうも「ゼロカロリーのピーちゃん」です。
一週間お休みしている間にひまわりが伸びていました。すごい成長。
暑いのといい雨が降りまして、一週間お水もあげてないです。次の水やりは水曜日の午後かなぁーと思います。

ふるさと納税の返礼品
どうも。「かんりしゃ」です。
梅雨です。暑すぎる。。。
カレーのデリバリーで体力奪われます。
前々からお伝えしていましたが「こくりのレトルトカレー」が、藤井寺市のふるさと納税の返礼品に採用されました㊗
市役所の方にいろいろとご尽力いただきました。
本当にありがたいです。
No.263 こくりのレトルトカレー(4食セット) / 惣菜 食品 手軽 レトルト カレー 玉ネギ 大阪府 特産品 – 大阪府藤井寺市|ふるさとチョイス – ふるさと納税サイト (furusato-tax.jp)
こくりのレトルトカレー(4食セット) | 大阪府藤井寺市 | ふるさと納税サイト「さとふる」 (satofull.jp)
↑これらのサイトから応募できます。
そして、さきほどついに注文がありました。
詳しくは言えないのですが、レトルトカレーが遠くに旅立ちました。
藤井寺市よ、よい税金の使い方してや!!!
今年も、レトルトカレーを作成中です。
ふるさと納税の返礼品の制度はどんどん変わるため、必ずしも次もOKかは分かりませんが、「藤井寺市と言えばこくりのレトルトカレー」と言えるくらいになるまで頑張ります!!
こんなことも含めて、日々めまぐるしいです。
めまぐるしー。
こくりのスイーツプロジェクト!!!お知らせ
どうも。「かんりしゃ」です。
ご好評いただいている「こくりのスイーツプロジェクト」ですが、7月はお休みします。
と言いますのも、開催日時が分かりにくい、というお声を多く頂き、「その通りやなー」と思ったからです。
開催日時は、「第〇火曜」など明確にし、年間で予定をたてて、お知らせしようと思い直しました。
その広報の準備を、7月中でします。
もし間に合わなければ、8月もお休みさせてもらうかもしれません。
再開したころには、新たなメニューも加わるかもです。お楽しみに。
では、またお知らせさせていただきます。
よろしくお願いします。
少し時間あいたから書く日記
どうも。「かんりしゃ」です。
現在、「かんりしゃ」は仕事中です。けど日記を書く時間ができたので、何かのりで書いてみます。
この感じ、久々です。
「かんりしゃ」はもう少しで大台の年齢になります。
年齢なんてものを気にしない、どてらい人になりたいのですが、そこまでどてらくなく、やや不安で感慨深くもあります。
みんなによく言ってますが、自分から「老いた」とは言わず、永遠の若手でいようと思っていますが、きっと老いていくのでしょうね。
こくりの一部のスタッフから「「かんりしゃ」の時代は終わった」と言われ、そういうこくりになっているのは、良いことや!と思っているのですが、裏ではまだまだ「かんりしゃ」の時代です(笑)。
けど、少しずつほんまに「「かんりしゃ」の時代を終えていく」必要はあると思っています。
まだまだ体力も気力も有り余っていますが、若い人が中心で、「かんりしゃ」がいなくても、よい味わいが残るこくりになっていって欲しいです。いやまだまだ「かんりしゃ」もおるけどな。いつかね。
細かい、悩むことは多いけど、けどなぜか出会った人と、何かをつないでいくという、何かすごい感動的なことに比べたら、その悩みも大切なつなぐもののうちの一つになるような気もします。
「会えて良かった」と思い合えたら、やっぱうれしいですね。
そろそろ終わろう。
いいリフレッシュの記事になりました。
これからもよろしく!